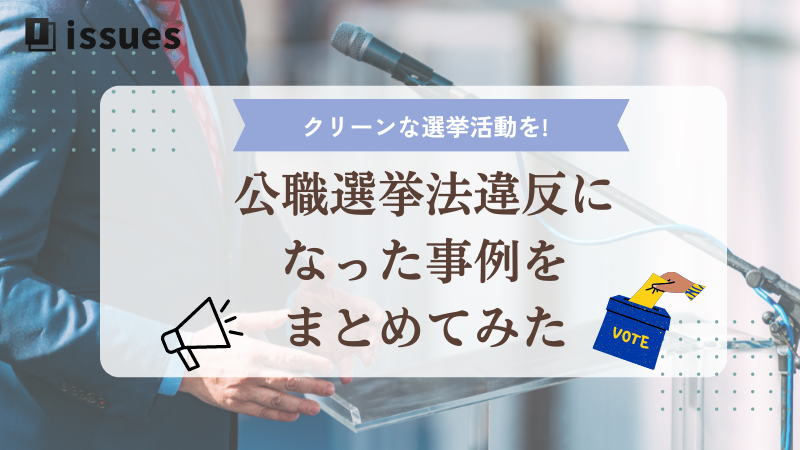2024年の選挙を振り返る:「石丸現象」に学ぶ東京都知事選挙
.png)
「石丸現象」に学ぶ、地方政治における新時代の選挙戦略
2024年の東京都知事選挙において、前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が、新人候補でありながら現職の小池百合子氏に次ぐ2位という結果を残したことは、従来の政治常識を大きく揺るがしました。この「石丸現象」と呼ばれる動きは、特に若者や無党派層から強い支持を獲得した点が特徴であり、地方議員にとっても「これからの政治コミュニケーション」を考えるうえで極めて示唆的だと感じたので、今回この記事を執筆させていただきました。ぜひ最後までご覧ください!
1. SNSと新メディアを駆使した選挙活動

石丸氏が注目された最大の要因は、SNSやYouTubeといった新メディアを積極的かつ効果的に活用したことでした。調査によれば、石丸氏の支持者のおよそ半数がYouTube動画を情報源として挙げています。これは、テレビや新聞といった既存メディアのフレームを越えた、まったく新しい政治情報の受け取り方が有権者層に定着しつつあることを示しています。
こうした流れは、地方議員にとっても重要な示唆を与えます。地方選挙でも、YouTubeやTikTok、Instagramなどのプラットフォームを通じた動画配信やライブ配信は、地域の有権者に生の声を届ける好機となります。特に若年層はインタラクティブで視覚的なコンテンツに共感しやすく、SNSを用いることでこれまで届かなかった層に効果的にアプローチできます。
2. インタラクティブな街頭演説と「祭り」化する支持拡大

石丸氏の街頭演説は、従来の「一方的な訴え」から脱却し、対話や参加を重視したインタラクティブな手法で有権者との距離を縮めました。SNS上では「石丸祭り」と呼ばれる一連の動画・投稿が拡散され、結果として新人であっても強力な支持を得ることが可能であることを証明しました。
地方議員においても、これまで形式的になりがちだった街頭活動を工夫し、「地元の声に耳を傾ける」「参加型の政治」を演出する試みは有効です。ミニライブ配信、コメントへの即時応答、インスタント投票機能などを組み合わせ、有権者が「自分が政治を動かしている感覚」を得られる場を作り出すことが、信頼と支持拡大につながります。
3. メディア・フレームからの脱却と無党派層への訴求

メディアは当初、小池氏や蓮舫氏を中心とした「2強対決」といった構図を描く傾向がありました。しかし実際には、石丸氏が無党派層から高い支持を集め、これが選挙後に明るみに出たことで、既存メディアの報道枠組みが有権者心理を十分に捉えきれていなかったことが浮き彫りになりました。
地方議会選挙や首長選挙でも、無党派層は一定数存在します。これらの有権者は、伝統的な政党支持にはとらわれず、むしろSNSなどから直接的なメッセージを求める傾向があります。報道フレームに左右されない独自の発信を行うことで、地方議員も「もう一人の有力候補」として浮上する可能性が開けます。
4. ネット広告・切り抜き動画と情報拡散の多層化

石丸陣営では、ネット広告を用いて動画の視聴回数を増やし、支持者が切り抜き動画を独自に拡散することで、さらなる支持拡大を実現しました。SNSが現代政治において不可欠な存在になりつつある今、有権者が「シェアしたくなる」コンテンツを準備することが、地方政治の文脈でも重要です。特にショート動画は通常の動画活用に比べて再生数や拡散力が高いとされています。
今後、政治の世界でも活用が当たり前になってくる可能性は高いと考えられますね!
5. フェイクニュースと情報操作への対処

拡散力や無党派層に有効だとされた一方で、SNSは誤情報や感情的な煽りが急速に拡散しやすい環境でもあります。地方議員は、発信において事実確認を徹底し、公平性・透明性を担保する姿勢を明示することが欠かせません。有権者は信頼できる情報源を求めています。誤った情報や極端な偏向が選挙結果を歪めないよう、批判的視点と慎重な対応が求められます。
地方議員が今こそ取り入れるべきポイント
「石丸現象」は、新人でもSNSを軸とした新しい選挙戦略によって若者・無党派層にリーチできる可能性があることを示しました。地方議員の皆さまも、以下の点を参考に戦略を見直してみてはいかがでしょうか。
- SNSの積極活用:YouTubeやTikTok等での動画発信、ライブ配信やショートクリップを通じた鮮度の高い情報発信
- インタラクティブな活動:双方向性を重視した街頭演説やオンライン交流で有権者との距離を縮める
- メディアに頼らない自律的な発信:従来のマスコミ報道に依存しない、自前の情報発信ルートの構築
- 若年層・無党派層への訴求:既成概念にとらわれず、親しみやすく共感を呼ぶメッセージで新たな支持者層を開拓
- 情報の信頼性確保:誤情報や偏った見解への対策を強化し、公平性・信頼性を担保
これらの取り組みを進めることで、地方議員も「新時代の政治コミュニケーション」を実現し、有権者からの信頼と支持を着実に高めていくことが可能となるでしょう。
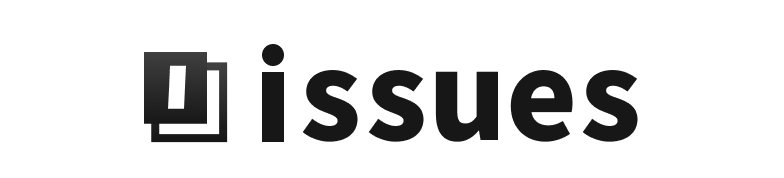
.png)