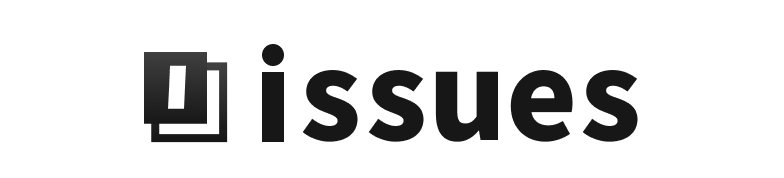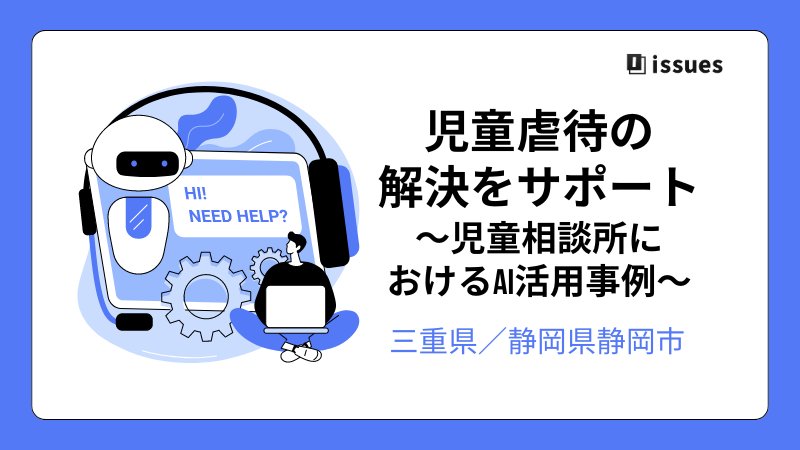静岡県の津波対策、ここがすごい!4選をご紹介

「防災先進県と呼ばれる静岡県。何がすごいのか知りたい!」
静岡県では「地震が起こる」ことを前提に、早くから津波被害を最小限に抑える対策を進めてきました。地域の特性に合わせた対策に、全国から注目が集まっています。
この記事では静岡県の津波対策の中から、
□話し合いがベースの静岡方式
□景観や自然にも配慮した静岡モデル
□小学校での防災教育
□オレンジゾーンでの取り組み
についてご紹介します。
最後までお読みいただくと静岡県の津波対策がよく分かり、ご自身のお住まいの地域で活用できるヒントが得られますよ。
「短時間」で「高い」津波予測

南海トラフ地震では静岡県のほとんどの地域で10m以上の津波が予測されます。
静岡市駿河区で12m、清水区で11m。一番高いと予測されるのは伊豆半島に位置する下田市。最高津波高33mと言われています。
さらに問題なのは、津波到達までの速さ。伊豆半島で影響が出始めるのは地震発生4分後。南伊豆町では最大津波到達時間は地震発生の7分後と言われています。「命を守る」ため一刻の猶予も許されません。
「地震・津波は必ず来る」前提のもと、静岡県では被害を最小限に抑える取り組みに力を入れています。
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/853/kaisetsu.pdf
【ここがすごい①】津波対策は話し合いで決める「静岡方式」
「静岡方式」には3つの特徴があります。
①地域の文化・歴史・風土および暮らしに根ざしていること
②自然との共生、および環境との調和との両立を目指すこと
③地域の意見を取り入れ、市町との協働ですすめること
地域の特性と住民のニーズを大切にしながら、住民と自治体がワンチームで取り組んでいます。それぞれの自治体の取り組みの一例をご紹介します。
浜松市

低地に広がる浜松市は、地震発生から18分で津波が海岸に到達、最大津波高15m、JR浜松駅付近まで津波が及ぶことが想定されています。
市内が浸水してしまうと、仮設住宅の建設にも時間がかかります。そこで、内陸部に仮設住宅用の台地を造成しているんです。さらに造成で出た土砂を混ぜたセメントで防波堤を作っています。
袋井市

南海トラフ地震では袋井市で最高津波高10mと予想。
江戸時代の津波で、「命山」のおかげで住人の命が守られた歴史があります。そこで、現在4つの「平成の命山」を整備しています。
伊豆半島

南海トラフ地震では伊豆半島にある下田市で最高津波高33m、南伊豆町で26mが予測されています。高い津波が見込まれるのであれば高い防波堤が必要、と考えるかもしれません。
伊豆半島では住民から、防波堤を作ると、漁業や観光の妨げになるとの意見がありました。そこで、防波堤を作るのではなく、避難路・避難場所を確保して「逃げる」ことを最優先した訓練に力を入れています。
「静岡方式」では、みんながWin-Winになれる防災対策を模索、実行しています。
https://www.jt-tsushin.jp/articles/interview/jt12_kawakatsu
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/3/2/bosai/1466817404364.html
【ここがすごい②】静岡モデル~浜松市の事例から~
防波堤というと「コンクリートで作られた無機質なもの」を思い浮かべる方が多いと思います。「静岡モデル」は景観に配慮した防波堤です。
浜松市では自然と一体化した防波堤を造設。標高13〜15mの盛り土をつくり、その上に木を植えます。木々が育つと災害防災林へ。さらに自然環境にも配慮しています。
浜松市の場合、整備前は沿岸全域で浸水深2m以上、東海道新幹線まで浸水が想定されていました。整備後は浸水深2m以上のエリアを98%減少。残り2%は避難タワーを整備することでカバーできるようになりました。
ハードとソフト面の整備で災害に立ち向かっていく事例として、参考になりますね。
ふじのくにメディアチャンネル
https://www.jt-tsushin.jp/articles/interview/jt12_kawakatsu
https://fmc.pref.shizuoka.jp/fujinokuni/number_50/3476/
【ここがすごい③】小学校から防災のカリキュラム

静岡県は学校教育の中にも「防災」を学ぶカリキュラムを組んでいます。防災対策は幼少期から必要なものだからです。
静岡市中島小中学校の例をご紹介します。中島小中学校は海に面した学校で、地震があればすぐに避難が必要な場所にあります。
中島小中学校で組まれているカリキュラムがこちら。
(PDF:https://nakajima-e.shizuoka.ednet.jp/aspsrv/asp_news/news.asp?DATE=20210325&ID=6&ct=%96h%8D%D0%8Aw%8FK%83J%83%8A%83L%83%85%83%89%83%80&nid=3)
自分の身を守り、そしてお互いに協力しあうことを学んでいきます。
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/todoufuken/data/22shizuoka/22-10/22-10-1.pdf
【ここがすごい④】伊豆市のオレンジゾーンは安心エリア

南海トラフ巨大地震が発生すると6分後に高さ10メートルの大津波に襲われると言われている伊豆市。
平成30年3月静岡県伊豆市の土肥地区は、全国で初めて「津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)」に指定されました。オレンジゾーンは病院、老人保健施設、幼稚園、学校などを建築する際に、「居室の床面の高さが津波の浸水以上」という規制があります。
オレンジゾーンと聞いて、「大丈夫かな?」と不安な気持ちもあるかもしれません。オレンジゾーンに指定されたことで、土肥地区の津波への安全性は格段に高くなり、防災対策をしていることが他地域との差別化にもなっています。
防波堤がない土肥地区では、津波が起こった際は宿泊施設の高層階に避難できるよう協定をむすんでいます。観光客を速やかに避難させる対策です。
津波のリスクを受け入れつつ、観光と防災を両立させるまちづくりを進めています。
https://www.city.izu.shizuoka.jp/material/files/group/38/1_suishinkeikaku.pdf
「災害は必ず起こる、今起こる」
津波対策に行政と住民がワンチームで取り組む「静岡方式」、自然と一体化した防波堤作りを目指す「静岡モデル」、学校教育における防災カリキュラム、オレンジゾーンでの取り組みをご紹介しました。
防災に必要なものを建設するだけでなく、避難訓練や防災意識といったソフト面からもアプローチしている静岡県の取り組み。「津波がきても防波堤があるから安心」といった意識では救える命が救えません。だから県民全員が「津波がきたら逃げる」という意識を育てて行くことが大切なのですね。
ぜひお住まいの地域の防災のヒントにしてみてくださいね。
issuesでは、南海トラフ地震の対策をしてほしいというトピックから、お住いの自治体の対応状況などについて議員の方へ声を届けることができます。