KKZ(勘・経験・前例)からの脱却!データで政策を強化するEBPM実践と課題について
-1.png)
8月開始の官民共創勉強会「その政策にエビデンスはありますか?根拠に基づく政策作りEBPM行政導入のコツ」にご参加いただけなかった地方議員の皆様へ、勉強会の内容を今後の活動に活かせるようにまとめました。
急速な社会変化とリソースの制約に直面する今、客観的なデータ(エビデンス)に基づき政策を立案・検証するEBPM(Evidence-Based Policy Making)は、地域運営の喫緊の課題を打破する推進力となり得ます。皆様の地域運営における具体的な一歩を踏み出すための専門的な面談機会を、ぜひご活用ください。
今回の講師のご紹介
講師:池畑光紀氏
地方行政経営研究所のEBPM事業責任者として、自治体の基幹情報システムのデータを匿名化&分析&可視化するAcrocityBIの企画・設計・運用を主導。全国30以上の自治体の地域課題解決を支援。
講師:近藤雅人氏
株式会社ビーコンラーニングサービス代表取締役。行政組織向けの研修の第一人者として年間1,000名を超える自治体や公共団体の職員向けの研修を監修・登壇。EBPMを活用できる組織作りのプロフェッショナル。
--------------------------------------------------------------------------------
1.直面する社会課題:矛盾する行政運営と地方自治の危機

現在、地方自治体が置かれている環境は、まさに大きな転換期を迎えています。
行政に求められるサービスの幅は広がり、課題は複雑化、高度化しています。しかし、地域課題に向き合うために必要なリソース(人、物、金、時間)は限られています。この「やることは増えるが、使えるリソースは限定される」という「矛盾への対応」こそが、今の地方自治が抱える最大のキーワードです。
特に日本は、少子高齢化による未曽有の危機に直面しており、都心部を除き、ほとんどの地域で人口減少が進んでいます。人口減少は税収の減少に直結し、財政が縮退していく時代に突入しています。
こうした状況において、これまでと同じやり方、すなわち根拠の希薄な政策立案を続けることは、地域のサステナビリティを担保できなくする「致命的な状況」であると言えます。
2.政策立案の転換点:KKZ(勘・経験・前例)からの脱却

財源が厳しくなる中、行政運営においては、何を行うべきか、何を思い切ってやめるべきかという「選択と集中」が必須となります。これを行うには、一貫性のある明確な判断基準が必要です。
しかし、現在の多くの自治体では依然として、意思決定が「勘と経験と前例(KKZ)」に基づいているケースが少なくありません。
特に、実務レベルである実施計画において数値目標を設定している団体は、全国の市区町村のうち28.7%に過ぎないというデータがあります。数値目標が設定されていなければ、事業の現状把握や目標設定ができず、その有効性も測定できません。結果として、各事業の優先順位も分からなくなり、メリハリのある財政運営が不可能となります。
EBPMは、こうしたエピソード(局所的な事例や体験)に基づく判断から脱却し、客観的に検証された証拠やデータ(エビデンス)を根拠として政策立案を行うための取り組みです。
3.EBPMがもたらす組織変革と住民サービスの質の向上

EBPMの導入は、限られたリソースを最も効果的に活用するための判断基準を提供し、行政組織全体に大きな変革をもたらします。
EBPMには、主に以下の3つのメリットがあります。
1. 財源の効率的・効果的活用: データに基づいて事業の実施・廃止を判断することで、限られた財源を効果的・効率的に活用できます。
2. 市民からの信頼獲得: 予算の使い道をデータで明確に説明し、その効果を検証することで、市民からの信頼を高め、安心感を提供します。
3. 組織運営と職員の活性化: EBPMによりPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)の質が高まります。効果が期待できる事業に集中することで、職員が自身の仕事のやりがいや貢献実感を高め、職員の離職問題の解決にもつながります。
こう言った観点から、EBPMの推進は、自治体組織を変化に強い組織へと変革していくための強力な推進力となり得るのです。
4.住民データ活用による政策推進と具体的な成功事例

地方自治体が保有する住民情報は、EBPM推進における最大の財産、すなわちビッグデータです。住民一人当たり年間5,000項目ものデータが蓄積されていますが、この膨大で複雑なデータを取り扱い、分析し、政策に活かす作業は、職員にとって非常に大きな負担となっています。
この負担を軽減し、職員が地域課題の解決に注力するために、データ収集・加工・可視化を自動化するBIツールなどの活用が進んでいます。
データ活用による成功事例の一部をご紹介します。
|
課題区分
|
具体的な課題とデータ活用
|
成果
|
|
デジタル化推進
|
マイナンバーカードの取得率向上。
|
データ分析により、高齢者や自動手当受給世帯など、取得率が低い層を特定。高齢者には出張補助、自動手当受給者には関連書類にPRチラシを同封するなど、ターゲットを絞った効率的な施策を展開し、効果をデータで検証しました。
|
|
地域経済の活性化
|
プレミアム付き商品券の売れ行き不振。
|
データ分析の結果、初期の購入単価が高すぎることが判明。購入単価を下げたり、電子での少額課金オプションを設定したりするなど、ニーズに合わせた販売戦略を展開し、第2弾で完売を達成しました。
|
|
都市政策
|
公共施設の建替えや利用状況の最適化。
|
街づくりセンター(公民館)など公共施設ごとの利用状況データを可視化。利用が活発な施設を優先的に改修計画に反映させたり、部屋ごとの利用頻度を分析して、将来の施設に必要な部屋数(和室や会議室)をデータに基づいて判断できるようにしました。
|
【目黒区の事例:公共施設のデータ公開】
東京都目黒区では、EBPM推進の一環として、持続可能な施設運営について住民と共に議論する土台を整えるため、「施設データ集」利用料・手数料などの収入といった詳細なデータが含まれています。これにより、情報の非対称性を解消し、施設運営の議論の質を高めています。
5.導入・推進の鍵:現場のリアルな声と組織文化の醸成

EBPMを組織に根付かせ、成果を出すには、文化の醸成や人材育成を含めた総合的な取り組みが不可欠です。推進には、以下の5つの観点からの取り組みが必要となります。
1. トップ(首長クラス)の協力とコミットメント
2. 管理職層の意識改革
3. データ分析や仮説設定ができる人材育成
4. データ基盤の整備(BIツールなどの導入)
5. 日常業務(予算申請など)へのデータ活用プロセスの徹底
【目黒区との対談ハイライト:若手の声と恐怖の克服】
東京都目黒区では、EBPMの導入は必ずしもトップダウンではなく、若手職員が集まる勉強会での強い問題意識の議論を通じて、その必要性が提言され、実現に至りました。
導入当初、現場では「データがあれば分析は簡単にできる」という認識がありましたが、推進過程で、データが可視化され評価の対象となることへの「恐怖」から、データ共有に消極的な部署が出現するという現実的な壁に直面しました。これに対し、目黒区では、あくまでも統計的なデータ活用であることを整理し、使い道を丁寧に調整することで乗り越えていきました。
目黒区の推進担当者(武山様)は、EBPMはこれまでの行政運営をすべて否定するものではなく、「エ
ピソードベースの経験を土台としつつ、そこに客観的なエビデンスを掛け合わせることで、さらに良いものにしていこう」という姿勢が重要であると強調されています。
【議員からの質疑応答ハイライト】
• 地域差がある自治体での効果: 人口密度や地域差が大きい自治体ほど、EBPMは有効です。地域ごとの特性や課題(例:マイナンバーカードの普及率の違い)を細かく把握し、地域に合わせた「絞り込み」の施策を打つことができるようになるためです。データツールは、住民情報と住所情報などをリンクさせ、詳細な地域別の分析を可能にします。
• 議会との連携と情報の非対称性: 現在、行政側と議会側の双方がEBPMツールを利用している事例は少ないですが、行政側が出したデータを議会に提示するケースはあります。目黒区の事例では、公共施設ごとの運営費や利用状況などのデータをオープン公開しており、情報の非対称性を解消し、持続可能な施設運営について住民と共に議論する土台を整えています。
• 医療分野での経費削減: 医療分野ではEBM(Evidence-Based Medicine)が定着していますが、地方自治体の健康保険事業において、データを使って具体的な経費削減効果を細かく検証できた事例はまだ少ないのが現状です。しかし、一部の団体では、温泉クーポン配布など健康増進策の効果(医療費削減につながっているか)をデータで検証する取り組みが少しずつ出てきています。
6.次の一歩へ:個別相談を通じた社会課題解決へ

EBPMの導入と推進は、単純なツールの購入ではなく、複数年を要する組織変革のプロジェクトです。内部リソースだけでの推進が難しい場合が多く、豊富な経験を持つ外部専門家の支援が不可欠です。
本勉強会にご協力いただいた企業様は、非営利組織に特化し、EBPM推進を支援する専門知識とノウハウを有しています。彼らは、全国の自治体でEBPM関連の100を超える利用事例の蓄積があり、初めての取り組みでもスモールスタートから着実に推進できるよう、伴走支援サービスや研修を提供しています。
地方議員の皆様には、EBPMの重要性を議会内で発言し、組織のキーパーソン(首長、課長、部長クラス)と専門家をつなぐ橋渡し役としての役割が期待されています。
地域の未来に向けた第一歩を踏み出すために、ぜひこの機会に、ご協力企業様との個別面談をご検討ください。来年度の予算編成や具体的な施策立案に向けた課題、あるいは組織文化の変革に関するご相談など、どんな小さな疑問や懸念でも結構です。
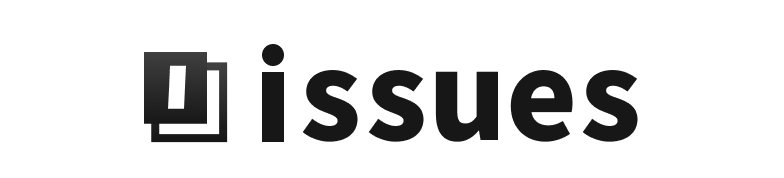
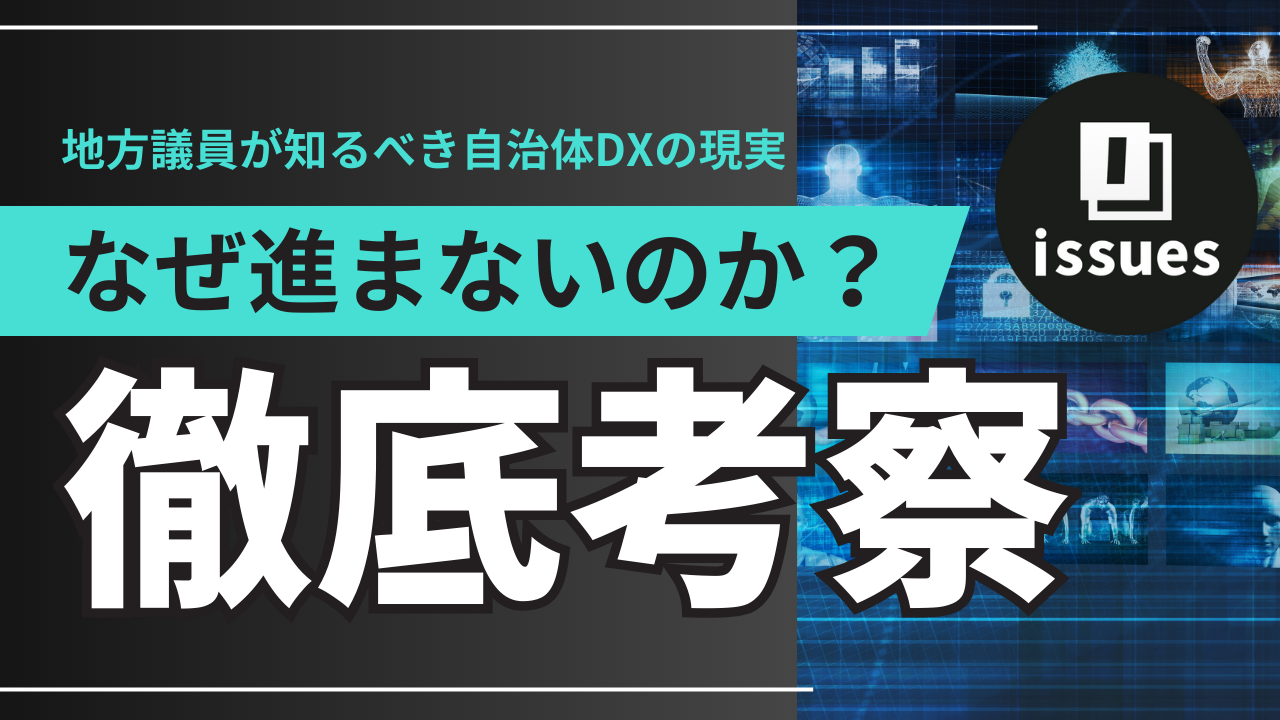
.png)