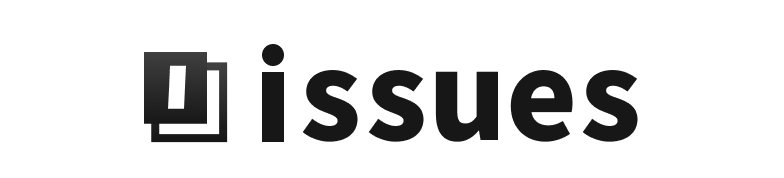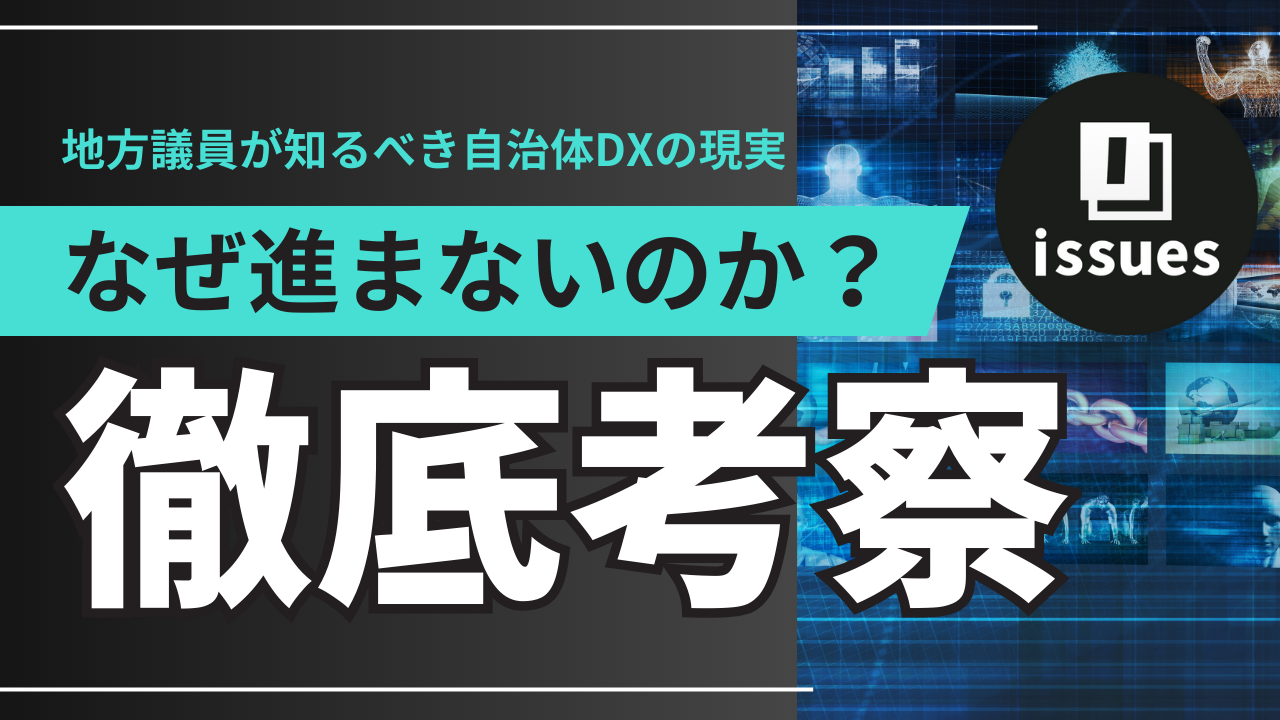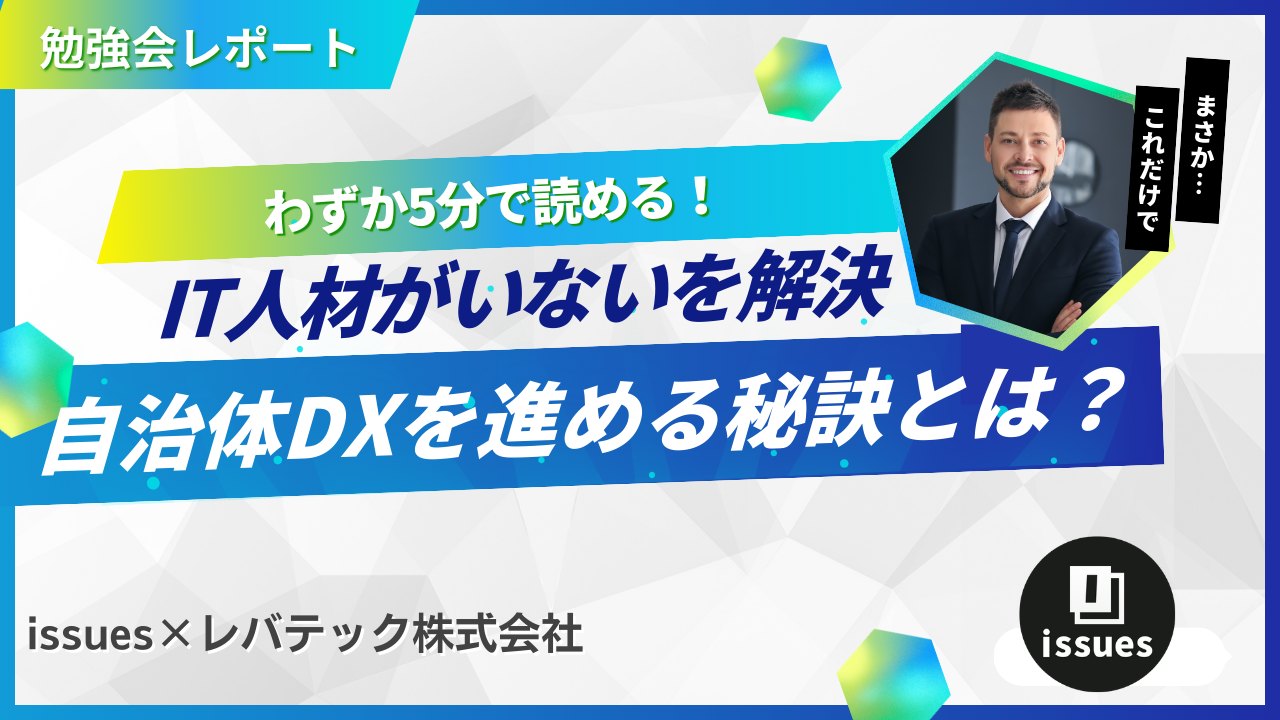2030年までに達成したい、再生エネルギー事業に関するまとめ
.png)
この記事は、issuesの官民共創勉強会「再生可能エネルギー 2030年の政府目標と地域での推進方法」ウェビナーに参加できなかった地方議員の皆様へ、講演内容、事例紹介、質疑応答の要点を凝縮してお届けします。
昨今直面している気候危機は、温暖化に留まらず、洪水や異常な猛暑といった異常気象や災害としてすでに顕在化している社会課題です。
この危機を解決する鍵こそが、再生可能エネルギーによる「エネルギーとお金と仕事の地産地消」戦略です。本勉強会では、日本の地域エネルギー自立の先駆けである長野県飯田市の「おひさま進歩エネルギー」の具体的成功事例と、その実現方法について深く掘り下げました。
1. エネルギーの転換機と地域が直面する気候危機

世界は今、太陽光発電、風力、蓄電池、そして電気自動車(EV)といった技術の爆発的な進歩を遂げています。
特に、太陽光発電の累積設置容量はわずか10年間で12.5倍に増加し、累積設置量は2024年中に世界の揚水発電の蓄電量を超過する勢いで増加しています。EV車販売比率も2014年の0.3%から2024年には22%まで急増しています。
国際的な目標も野心的です。2023年に開催されたCOP28(UAEコンセンサス)では、2030年までに世界の再生可能エネルギー設備容量を現在の3倍(3,400 GWから11,000 GWへ)に拡大することが合意されました。
気候危機は、温暖化に留まらず、洪水や異常な猛暑といった異常気象としてすでに顕在化しています。国際基準のクリアを達成するのは困難ですが、地元の理解を得つつ取り組んでいくことが重要とされています。
2. エネルギー自立がもたらす経済安全保障上のメリット

日本では再生可能エネルギー(再エネ)導入に対する消極的な見解も見られますが、再エネによるエネルギーの自立は、気候危機への対応だけでなく、地域や日本全体の経済的・安全保障的なメリットが非常に大きい点が重要です。
日本が現在抱える最大のリスクの一つは、エネルギー供給の海外依存度です。昨年度、日本は化石燃料輸入に30兆円を費やしており、これはGDP(国内総生産)の約5%に相当します。さらに、食料輸入で12兆円、デジタル赤字(サービス赤字)では昨年5.9兆円のマイナスが生じています(このデジタル赤字は2035年には18兆円に達する可能性があると予測されています)。
再生可能エネルギーは、一度設備を導入すれば燃料を海外から輸入する必要がなく、純粋な国産エネルギーとして地産地消が可能です。これにより、地域外や海外へ流出していた巨額の「エネルギー支出」を地域内にとどめ、地域経済でのお金と仕事の循環(経済乗数効果)を生み出すことが可能となります。これは、原子力発電がウランを輸入しているため輸入エネルギーであるのに対し、再エネは純粋な国際エネルギーであるという点からも、国益として優先すべき施策です。
3. 地域が目指すべき「エネルギーとお金と仕事の地産地消」の原則

地域が自立を目指す上で欠かせないのが「エネルギーとお金と仕事の地産地消」です。日本の再エネポテンシャルは極めて高く、環境省の調査によれば、太陽光だけでも日本の全電力供給量(1170 TWh)の約300%(3311 TWh)を賄う可能性があります。特に、そのうちの86%(2861 TWh)は農地(荒廃農地を含む)が占めています。
しかし、過去の再エネ導入では、ずさんな制度設計(FIT制度における認定時点での高額固定価格決定など)の結果、「バブルと乱開発」を生み出し、余分な国民負担(FIT賦課金のうち最大62%が初期の高額な太陽光案件によるもの)や環境破壊、地域社会との対立を招きました。
この失敗の教訓から、地域での再エネ推進には、デンマークの事例に学んだ「ご当地エネルギー3原則」の徹底が不可欠です。
1. 地域社会のオーナーシップ(所有権または自分ごと意識)
2. 重要な意思決定への参加
3. 「利益」と「良いこと」は地域社会で分かち合う(便益の分配)
そして、開発に関しては、山を切り開くのではなく「すでに人の手が入った場所を優先する」ことが大原則となります。具体的には、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)として農地を有効活用することなどが挙げられます。
4. 地域エネルギーハブの実現事例:長野県飯田市のケース

地域主導で再エネ事業を成功させた先駆的な事例が、長野県飯田市で2004年に設立された「おひさま進歩エネルギー」です。
飯田市では、行政施設(保育園、公民館など)の屋根に太陽光を設置する日本初のオンサイトPPA(電力購入契約)事業をスタートさせました。地域金融機関の融資と市民出資を活用し、発電設備の工事を地元の企業に発注することで、地域内にお金と仕事の循環を生み出すことに成功しています。
飯田信用金庫の当時の理事長は「当金庫がおひさま進歩に融資したお金が地域の工事会社の仕事となり、当金庫の顧客から支払われる電気代から返済される」という、地域内のお金と仕事の循環が目に見えると述べています。
具体的な経済効果として、おひさま進歩エネルギーの設立と活動により、2013年から2020年の7年間で地域のエネルギー自給率は3ポイント向上し、地域外へのエネルギー支出の流出が283億円から224億円に下がり、エネルギー経済収支は59億円改善しています。
さらに、この取り組みは経済効果に留まりません。防災センターの屋根に設置した設備で災害時に自立運転できる訓練を住民と共に行ったり、中学校で生徒自身が「学校の屋根に太陽光発電をつけて温暖化防止に役立てる」という公約を掲げて当選し、環境学習に繋げたりするなど、教育や防災の面でも大きな成果を上げています。
5. 地域社会の信頼と自立を勝ち取るためのポイント
本勉強会では、地域での再エネ事業推進に関する具体的な疑問が議員の皆様から寄せられました。
(1) 再エネ100%は本当に可能か?
「再エネだけで電力100%を供給できない」という意見もありますが、専門家は可能といっております。これは、近年急速に安価になり性能が向上した蓄電池技術によって、太陽光発電の変動性(特に冬場など)を補うことが現実的になったためです。家庭の屋根に太陽光と蓄電池を組み合わせる「街中メガソーラー」の構想では、メガソーラー1基分に相当する余剰電気が地域で生まれ、その余剰電力を地域内で活用する仕組みも技術的に実現可能です。
(2) 事業体と行政の理想的な距離感は?
地域エネルギー事業を進める上で、行政との距離感は非常に重要かつデリケートです。行政が過半数の資本を持つ第三セクター化すると、行政の下請け事業になりがちです。飯田市の事例では、行政から直接的な資金や人員の応援はありませんが、行政施設の屋根の提供や電力供給の協定といった密接な協力関係を築いています。行政からの資本は5〜10%に留めつつ、地域の公益的な事業体として行政とフラットに連携する形が、自立的な発展のためには望ましいとされます。
(3) ソーラーパネルの廃棄・火災の安全性は?
廃棄問題に関しては、太陽光パネルは技術的には95%から98%30年〜40年後と予測されていますが、社会的な仕組みづくりを進めることで、十分に処理可能であるとの見解が示されました。予想される最終処分量は年間2万トンから5万トン程度であり、自動車の最終処分量(約100万トン)と比べても極めて少ない量です。火災の安全性についても、適切な手順を踏めば水による消火は可能であり、石油ボイラーなどに比べても特別に危険度が高いわけではないと説明されています。
6. 変革の担い手としての地方議員の皆様へ
飯田市の取り組みは、地域社会のリーダーである首長や議員が、市民と一体となって、環境文化都市という都市像を掲げ、取り組んだ意義を明確にしたからこそ実現しました。
地方議会での質問を通じて、この「エネルギーの地産地消」を政策の柱として打ち立てることは、地域が抱える課題を根本から解決する糸口となります。各自治体単位での行動を起こすことが求められているかもしれません。
--------------------------------------------------------------------------------
未来への第一歩:専門家との個別面談のご案内
今回のウェビナーを通じて、「自分の地域でも再エネを通じた自立的な地域づくりを推進したい」「具体的にどの政策から着手すべきか」といった疑問をお持ちになった議員の皆様へ。
本勉強会にご協力いただいた企業様は、長野県飯田市「おひさま進歩エネルギー」の立ち上げ支援にも関わった専門家と連携し、地域の特性に応じた政策作りと事業化のサポートを提供しています。
この個別面談は、貴地域で持続可能なエネルギー政策を推進していくための戦略的な知見を獲得し、理論を実践に移すための重要なステップです。飯田市のように地域自立に向けた具体的なロードマップを描き始めるための第一歩として、ぜひこの機会に専門家の知恵をご活用ください。