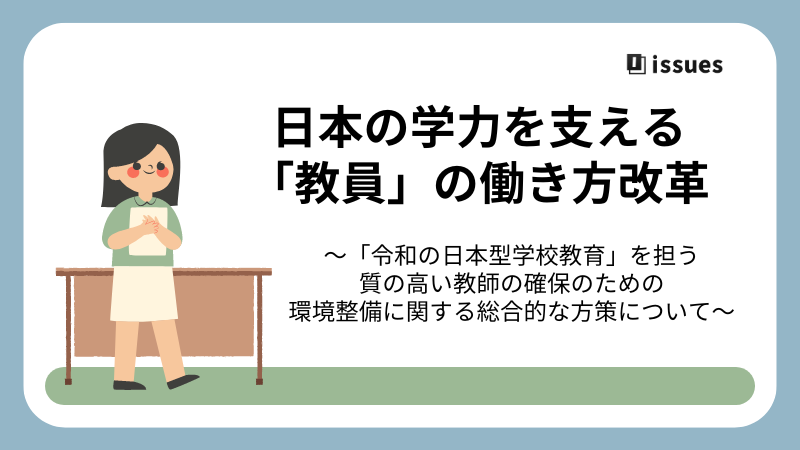「探究学習」とは?未来を切り拓く力を育む新たな学習
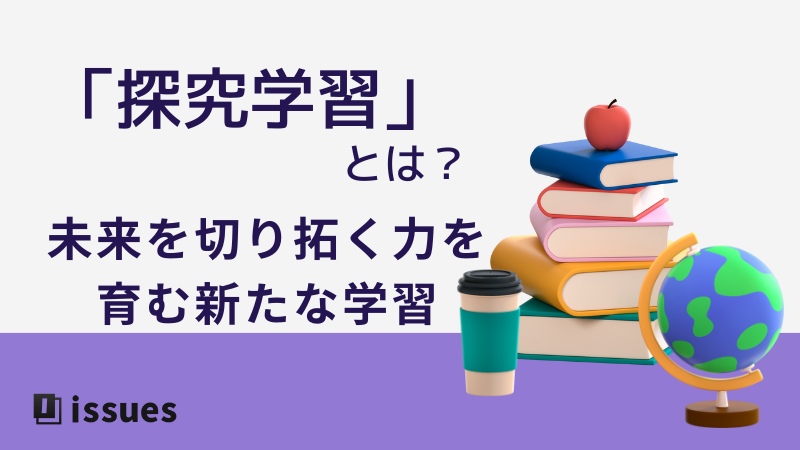
issuesの高松です。
現代社会は変化のスピードが速く、将来を予測するのが困難な時代です。こうした社会を生き抜くためには課題に柔軟に対応する力や、自ら答えを見いだす力が求められます。その力を養うための教育が「探究学習」です。
2022年に教育指導要領に盛り込まれ、小・中・高校で取り組んでいます。児童生徒は情報を収集・処理し、問題解決を図る力を身につけていきます。しかし一方で、探究学習には課題もあります。
この記事では、探究学習で身につく力と、今後の課題について詳しく解説します。お住まいの自治体の教育施策に役立ちますので、ぜひ最後までお読みください。
探究学習は未来を切り拓くための学び

探究学習は自分で立てた問いについて、情報収集・分析・意見交換をして、答えを見出す学習方法です。実社会で求められる「課題解決力」を育みます。
海外の研究では、
・子供たちの65%は将来、今は存在していない職業に就く
(キャシー・デビッドソン氏(ニューヨーク市立大学大学院センター教授))
・今後10年〜20年程度で、半数近くの仕事が自動化される可能性が高い
(マイケル・オズボーン氏(オックスフォード大学准教授))
といった予測があります。
探究学習は自らの人生を、自らの力で生き抜く力を培っていく教育でもあるのです。
探究学習で身につく4つの力

探究学習では4つの力が身に付きます。
1.自ら課題を見出す力
日常生活で問題点を発見する力が身に付きます。
教科学習では教科書を見れば答えがあります。しかし探究学習では自分で問題点を見つけ、解決していくしか方法はありません。
2.情報収集する力
問題解決に必要な情報を集め、選択する力が身に付きます。
インターネット、本、メディアなど、身の回りには情報があふれています。「一次情報は?」「デマではない?」と情報の見極めが必要です。
情報収集の力がつくと誤情報に流されることもなく、自分に必要な正しい情報だけを得ることができます。
3.得られた情報から答えを導き出す力
集めた情報を組み合わせ、客観的に分析し、課題解決のための最適解を考えます。さらに不足している情報がないか、考える力もつきます。
4.相手に伝える力
自ら見つけた問いを言語化して、言葉で相手に伝える力が身に付きます。
学校以外でも、メール、チャットなどテキストコミュニケーションや、社会に出てからのプレゼンテーションでも必要な能力が養われます。
今、求められる力を高める総合的な探究の時間の展開│文部科学省 令和5年
今さら聞けない!探究学習ってなに?考え方、目的、メリット│一般社団法人Fora
探究学習の一例
1.西東京ふるさと探究学習
(西東京市立保谷小学校3年生・ビオトープ探検隊)
保谷小学校ではビオトープの生き物や植物に関する調査活動を行い、生き物が暮らしやすい環境への改善策を検討する探究授業を行いました。
ビオトープを観察し、生き物や植物を調べていく子どもたち。その中で保谷小学校のビオトープのすばらしさを知り、下級生に良さを伝えるプレゼンテーションを行いました。さらに、地域でビオトープに詳しい方を先生にお呼びして、掃除やお手入れの方法を学び、ビオトープを魅力的に魅せるデザインも考えました。
2.市役所プラン
(富士市立高校2年生)
高校生が、富士市の「観光」「交通」「デジタル推進」「まちづくり」「子育て」「交流」「ジェンダー」「防災」の8つのテーマについて、問題提起と解決策を検討しました。
この活動では、市役所関係者、大学・大学院生、地域の方々に助言を求めたり、ヒアリングを重ねたりしながら、それぞれのグループで提案をまとめました。
例えば、富士市の製紙業を活かして外国人観光客を増やすアイデアが挙がりました。当初は製紙工場の見学プランが検討されましたが、見学可能な工場がほとんどないという課題が明らかになりました。そのため宿泊施設で製紙制作体験の無料クーポンを配布するなど、地域の資源を活用したアイデアを新たに考案しました。
R5年度市役所プランレポート集.pdf │静岡県富士市 令和5年
3.生徒それぞれが進める探究学習
(宮城県気仙沼市教育委員会)
気仙沼市教育員会では生徒一人ひとりが課題を設定して取り組む「探究学習」を行っています。
個別の探究活動はグループ以上に生徒へのサポートが求められます。地域のことをよく知る人材を「探究学習コーディネーター」として全市立小・中学校に派遣して、支援体制を作っています。
探究学習は本人の「やりたい」という自発的な動機付けが必要です。教員や探究学習コーディネーターがファシリテーター役として、生徒たちに問いを投げかけながら学びを深める役割を担っています。
日本全国の探究学習の事例紹介(地域課題編)│project design 令和5年
探究学習は教員への負担が大きいという課題も

探究学習は良い面しかないように見えますが、デメリットもあります。
NPOカタリバ(2022年12月-2023年2月/教員232名)の行ったアンケートでは、
・授業カリキュラムの設定に悩んでいる 61.3%
・調べ学習だけで終わってしまう 55.5%
といった課題が見えてきました。
探究学習、95%の教員が「課題を感じている」 NPOカタリバ、探究学習をサポートする全国の教員向けに実態調査│NPOカタリバ 令和5年
企業と組んだ新たなアプローチ

探究学習は学内だけでなく、企業と組んだ取り組みも始まっています。文部科学省のホームページでは、探究学習で活用できる外部資源が紹介されています。
企業とのコラボレーションで
・教員の負担が減る
・生徒児童の学びの選択肢が増える
といったメリットがあります。
鉄道会社と協力した街づくりの授業
(東京都渋谷区と東急株式会社)
東京都渋谷区は東急株式会社の支援を受け、令和6年11月から渋谷区立の小学校やN高等学校・S高等学校で「まちづくり」をテーマとした探究学習を実施しています。
「将来、どのようなまちが必要か」といった探究のメインテーマを掲げ、まちづくりの基本の考え方や企業の取り組みを知り、児童・生徒がチームごとに探究学習を進めます。そしてそれぞれのチームで発表する予定です。
「まちづくり」をテーマにした探究学習の授業支援を開始します | 東急株式会社のプレスリリース│東急株式会社 令和6年
ビジネスの構築を体験
MoonShot はソーシャルビジネスの 0 から 1 の構築を体験するサービスプラットフォームです。それぞれの学校の指導方針に合わせてカスタマイズされたプログラムを活用できるので、教職員が総合的な探究の時間に費やしていた時間を 80〜90%削減することが可能となります。労働負担の大幅な軽減が見込めます。
「教育を共育で変える」インパクトスタートアップ株式会社MoonJapan シードラウンドにて3,000万円の資金調達を実施│MoonShot 令和6年
探究学習がますます重要になる
この記事では探究学習のメリットとデメリット、取り組み事例をご紹介しました。探究学習はこれからの時代ますます必要になる授業です。しかし教員の負担が大きくなりすぎると、他の科目教科への影響も出てくるため、負担軽減の視点も大切です。ぜひお住まいの自治体での参考になさってみてください。
勉強会のアーカイブ動画をご覧になりたい方へ
12月19日・23日の日程で探求学習における教職員の現状と課題について勉強会を行いました。全編をご覧になりたい方は下記のフォームより必要事項を入力下さい。
エントリー、お待ちしています!
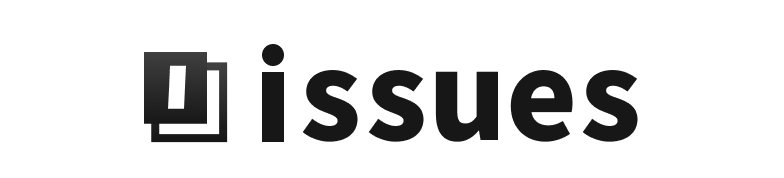

.jpg)