子育ての不安を放置しない。専門家が24時間寄り添う「オンライン相談」の解説
.png)
今、日本の妊娠・出産・子育て支援は大きな変革期を迎えています。核家族化、共働き世帯の増加、そして専門医の偏在と不足により、住民の「不安」や「孤立」という心理社会的な課題が深刻化しています。
本記事では、株式会社Kids Publicが提供する「産婦人科オンライン・小児科オンライン」サービスに関する勉強会の内容を元に、この危機を乗り越え、地域の子育て支援を「切れ目なく支える」ための具体的な解決策と、そのエビデンスを共有します。
1. 日本が直面する「心理的な健康」の危機
.jpg?width=640&height=427&name=24005626_s%20(1).jpg)
日本は身体的な健康水準は高いものの、子育て家庭を取り巻く「心理的な健康」において深刻な課題を抱えています。
孤立が引き起こす悲劇と専門家の不足
- 妊産婦の死亡原因第1位が「自死(自殺)」:2020年以降、妊産婦の死亡原因のトップは自死となっており、医学的な要因を超えて、精神的健康のケアが喫緊の課題であることが示されています。
- 産後うつの増加:出産後の母親の10人に1人が産後うつを発症しています。孤独や不安が背景にあり、これらはときに通院すら大変なケースも少なくありません。病院という「受け身の施設」で待っているだけの対応で果たしていいのでしょうか。
- 専門医の減少:過去12年間で、小児科診療所は16%、産婦人科診療所は20%減少しており、今後、リアル(対面)で専門医を確保することはより困難になります。
2. なぜ「産婦人科オンライン・小児科オンライン」が有効なのか

住民が本当に求めているのは、受診が必要な「診療」ではなく、日常的な不安を解消するための「安心」です。もちろん緊急性の高い、生死に関わること(痙攣がとまらない、39℃の急な発熱など)は病院にすぐ行くべきです。しかし、子どものちょっとした不安、例えば「子どもの発育が順調か知りたい」「鼻水が出たり引いたりといった症状が3週間続いている」などにはオンラインでの相談ができることに大きなメリットを感じる住民が多くいることも、また事実なのです。
2-1. 専門家が100%対応し、質の高い「安心」を提供する
kids publicのオンライン相談では以下の特徴があります。
- 専門家の100%保証:対応するのは、産婦人科医、小児科医、助産師の専門職のみです(2024年7月現在、256名以上が参画)。これにより、専門外の医師が回答し、結果的に「心配なら小児科へ行ってください」といった安易な受診勧奨に繋がることを防いでいます。
- 共感と質の管理:医学的な適切性と利用者満足度の両面をチェックしています。相談対応において「心配でしたね」といった共感的アプローチが満足度向上に極めて重要であることが研究で示され、徹底されています。
- 低ハードルの相談形式:最も利用が多いのは、24時間365日質問可能なテキストベースの「いつでも相談」であり、全相談の84.4%を占めます。これは、対面や電話よりも心のハードルが下がる、現代の保護者のニーズに合致しています。
2-2. 地方議員が注目すべきエビデンスと経済効果
住民にとってのメリットを以下に整理します。
| 項目 | 効果/実績 |
|---|---|
| 産後うつ対策 | 横浜市・東大との共同研究(RCT)により、サービス利用者で産後うつのハイリスク者が2/3に減少した(世界初の英文論文で発表)。 |
| 救急外来受診の適正化 | すぐに受診すべきと判断される割合が1.5%と極めて低い(子ども医療でんわ相談「#8000」の約25.7%と比較)。小児科医が動画・画像などの情報を含めて判断するため、安易な受診を大幅に回避。 |
| ハイリスク者の発見 | オンライン相談を通じて発見され、行政に連携されたハイリスク者(虐待、産後うつ等)の約半数は、自治体が把握していませんでした。 |
3. 自治体での導入実績

kids publicのオンライン相談は現在、全国40都道府県、232の市区町村に導入されており、地域の実情に応じた課題解決に貢献しています。
導入事例:医療過疎地から大都市まで
- 岩手県岩泉町(医療過疎地):町に実質的な小児科がないという住民の切実な声から導入。無料トライアル期間中、利用の55.2%が夜間に集中し、閉院後の「お守り」として機能。
- 横浜市(大都市):共働き世帯の増加に伴う、休日・夜間の相談ニーズの解消を目的に導入。エビデンスに基づき、生活満足度向上や精神的なゆとり創出に貢献。
- 東京都練馬区:23区で初めて導入。ICTを活用し、日中や区役所窓口が閉まっている時間帯の相談環境を充実させた事例。
導入時の重要論点と財政的支援
① 地元医療機関との連携 本サービスは「医療行為」ではなく「相談」であり、保険診療や地元の医療機関の患者を奪うものではありません。むしろ、利用が夜間や休日に集中するため、医療機関が対応しきれない時間帯の不安を解消し、救急外来の負担を軽減することで、地域医療を支えるという理解を得るための丁寧な事前説明が重要です。
② 財政的補助(補助率3/4) 地方自治体の財政負担を大きく軽減する補助制度が用意されています。
- 市区町村向け:こども家庭庁の補助金(利用者支援事業—妊婦等包括相談支援事業型)により、事業費の3/4が補助されます。
- 都道府県向け:厚生労働省の地域医療介護総合確保基金などにより、2/3の補助金が利用可能です。補助金は導入費用だけでなく、ランニングコストにも使用できます。
4. 地方議員の皆様への提言

このような仕組みを「ただ当てはめるのではなく、ちゃんとやる」ことで、この課題をチャンスに変えることができます。
地域の子育て支援体制の充実のために、ぜひ以下の行動をご検討ください。
- 一般質問での取り上げ:この内容を地域の課題として認識し、首長や担当部署に対して、妊婦等包括相談支援事業におけるオンライン相談の導入を提案する。
- 担当部署への提案:首長や担当部署(保健所等)に対し、本事業の費用対効果(医療費削減、行政コスト削減、社会的損失回避の三本柱)や、財政補助の情報を共有する。
- 無料トライアルの活用:導入の判断に先立ち、まずは無料トライアル(契約不要、最短4週間で開始可能)を検討し、住民の反応や職員の負担を実感する。
本記事で取り上げた産婦人科・小児科オンライン化を検討されたい方はkids public様に個別相談を行うことが可能です。お話を聞いたからといって、自治体に提言をする、強引な営業を受けるといったことは一切ございません。ぜひ、お気軽にご活用いただけますと幸いです。
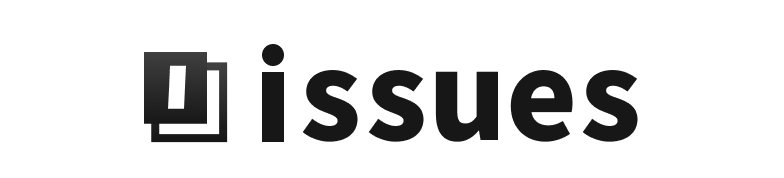

.png)